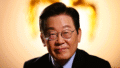人間中心主義を問い直した20世紀思想(note 2025年9月24日 07:30)
こたまる:AIとの共創マネージメント
“目標”も“自己”も完成することはない。エンタメ業界歴20年。とあるゲーム会社のマネージャー。哲学、内省や自己理解、マネージメントについて日々葛藤している過程を描いています。
戦争や全体主義といった極限状況で人間を見つめ直した哲学者たち
こんにちは、こたまるです。数多くの記事から目に止めていただき、ありがとうございます。
今回は「人間中心主義をどう問い直したのか」というテーマで、20世紀の思想をベルクソン アーレント フーコー メルロ=ポンティ カミュ この五人の哲学者に沿って整理してみます。
彼らが生きた20世紀前半から半ばは、
・科学主義の膨張(人間を機械とみなす視点)
・全体主義と戦争(人間を資源や数値に還元する暴力)
・冷戦と規律社会(人間を管理する制度)
が重なり合う時代でした。
いずれも戦争や全体主義といった極限状況を背景にしながら、人間を「ひとつの答え」ではなく「多様な像」として捉え直した人々です。
生命の流れを創造する存在 ― ベルクソン(1859–1941)
ベルクソンの思想は「持続」という概念に凝縮されています。
時間を機械の歯車のように分割可能とする科学主義に対し、彼は時間を流れる音楽のように経験しました。
意識は点の連続ではなく、絶えず重なり合う流れ。
そこから新しい行為や創造が生まれると考えました。
背景には産業化と科学信仰があり、人間は外部から決定される存在として矮小化されつつあったのです。
ベルクソンはそこに抗い、直観によって生命の内的流れを掴むことを強調しました。
彼の直観主義は後にメルロ=ポンティの「身体による世界経験」やカミュの「生の肯定」にも影響を与えています。
ベルクソンは 人間とは「未来を未定形のまま生み出す生命」であると定義したように思います。
私としてもとても共感ができます。
公共性を共有する存在 ― ハンナ・アーレント(1906–1975)
アーレントはナチス迫害から亡命し、無国籍を経験した哲学者です。
彼女は人間の尊厳を「労働」や「思考」ではなく、「行為=他者と新しく始めること」に見出しました。
孤立した個ではなく、他者と語り合い公共空間を築くことで人は人になる、という発想です。
アーレントはアイヒマン裁判を通じて「悪の凡庸さ」という言葉を残しました。これは悪を怪物的なものではなく、思考停止した日常の延長に見出したものです。
この観点は、権力装置を分析したフーコーや、全体主義に距離を置いたカミュとも響き合っているように見えて面白いなと感じました。
彼女は人間とは「他者と世界を共有することで人になる存在」であると捉えているように思ます。
情熱的で勇敢、同時に冷静な観察者。
議論を恐れず、公共性のために発言し続けた知性人でした。
権力に形づくられつつ自らを再構築する存在 ― ミシェル・フーコー(1926–1984)
フーコーは精神医学や監獄制度の歴史研究から出発し、「人間は自然に存在するのではなく、制度や権力によって構築される」と論じました。
人間は「権力に形づくられつつ、自己をつくり直す存在」であると見ているのかもしれません。
身体や欲望さえも規範の網に取り込まれているという視点は、伝統的な人間中心主義を根底から揺るがすものでした。
重要なのは、フーコーが「自由」を真実への到達ではなく「自己をどう生き直すか」と捉えた点です。
彼にとって主体とは固定されたものではなく、常に書き換え可能な「自己形成の実践」でした。
世界と交差する身体的関係存在 ― メルロ=ポンティ(1908–1961)
メルロ=ポンティは「知覚の現象学」を通して、人間を身体的な関わりの中に置き直しました。
世界は外から眺める対象ではなく、身体を通して交差し続ける場。知覚は主観でも客観でもなく、関係性の生成過程なのだと考えました。
ベルクソンの持続概念を参照しつつも、抽象的な時間ではなく、あくまで身体の触覚や運動感覚から思考を展開したのです。
この発想は、後にフーコーが制度による身体の生産を論じる土台にもなりました。
人間を「世界と交差しつづける身体的関係存在」と捉えています。
私にとってはこの「つづける」という可逆性が新鮮でした。
不条理に誠実に生きる存在 ― アルベール・カミュ(1913–1960)
カミュはアルジェリアの貧困層に生まれ、戦中にはレジスタンス新聞を発行して独裁に抵抗しました。
『異邦人』『シーシュポスの神話』で描かれるのは、意味を与えられない世界=不条理に直面する人間像です。
しかし彼は絶望に沈むのではなく、他者と連帯し節度をもって抗うことを人間らしさとしました。
英雄的な大義ではなく、日常的な誠実さの中に価値を見出す姿勢は、冷戦期の暴力的イデオロギーに対する批判でもありました。
「不条理を抱えながらも誠実に生きる存在」こそ人間だと捉えています。
5人の関わりと人間像の多極化
五人の思想は孤立していたわけではなく、互いに交わりながら「人間像の多極化」を形づくりました。
ベルクソンが一つ上の世代にあたるので、他の4人にも影響を及ぼしています。また、それぞれが同じ時代を生きたので、思想が共鳴し合い、またそれぞれの批判的な立場を保ちつつも多極化されています。
・ベルクソンの「生命の流れ」を重んじる直観主義は、メルロ=ポンティの「身体を通じた世界経験」に継承され、さらにカミュの「生を肯定する感性」にも響きました。
・アーレントは「公共空間での始まり」を強調しましたが、晩年のフーコーもまた「主体の自己形成」という形で近づき、両者は全体主義への抵抗を共有しました。
・フーコーは一方で、メルロ=ポンティの身体論を批判的に乗り越え、身体そのものが制度に生産されると論じました。
・カミュとアーレントは、時代を共有しながら「大義や全体主義に抗う倫理」を強調し、理念より人間の尊厳を優先する姿勢で共鳴しました。
つまり五人は、生命・公共性・権力・身体・不条理という異なる切り口から出発しつつも、共通して「人間を単一の原理に閉じ込めない」という方向で交わっていたのです。
疑うことで立ち上がるヒューマニズム
ベルクソンは科学主義へのアンチテーゼとして生命の流れを描き、
アーレントは全体主義へのアンチテーゼとして公共性を重視し、
フーコーは規律社会へのアンチテーゼとして自己形成を示し、
メルロ=ポンティは抽象主体へのアンチテーゼとして身体を基点に置き、
カミュは大義の暴力へのアンチテーゼとして誠実さを選びました。
20世紀は、人間中心主義を信じるために、まずそれを疑うことから始めた時代でした。
その軌跡を辿ることで、今の私たちがAI時代に改めて「人間とは何か」を考える手がかりにもなるのではないでしょうか。