 科学・技術
科学・技術 バイオマス発電とは? メリット・デメリット、交付金や導入事例を紹介
バイオマス発電が新時代の発電方式として注目を集め、投資や経営などさまざまな文脈で引き合いに出されることが増えてきた。バイオマス発電は、太陽光発電や風力発電にはない強みをもつ再生可能エネルギーであり、国が交付金などの支援制度を設けて普及を後押ししている。今回はバイオマス発電とは何か、どんなメリットやデメリットがあるのか、そして支援制度や企業の導入事例について解説していく。
 科学・技術
科学・技術 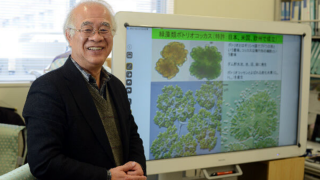 科学・技術
科学・技術 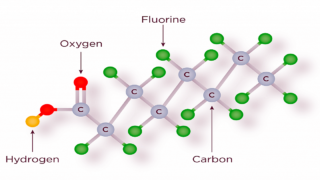 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術 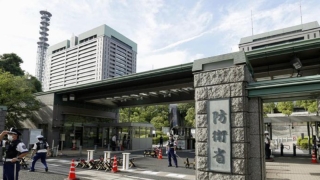 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術 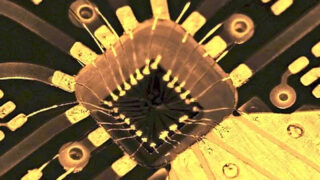 科学・技術
科学・技術 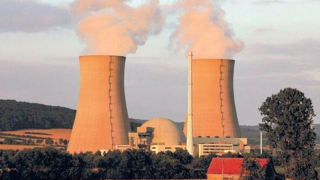 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術