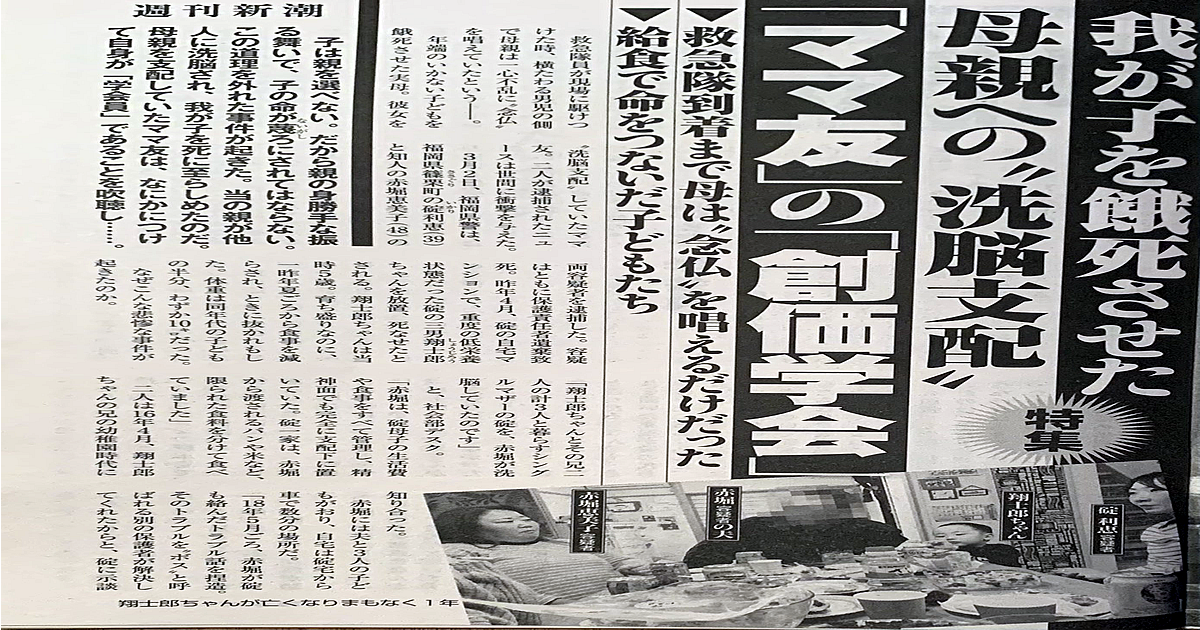他宗を「邪宗」と罵った創価学会は変わったか カギは排他性、攻撃性を超克できるか否かだ(東洋経済ONLINE 2022/11/01 6:30)
幼少期の話をしよう。私は、他の学会の子どもたちと同じく、親から「神社の鳥居をくぐってはいけません」「お賽銭を投げてはいけません」「他宗の神社で手を合わせてはいけません」などと教わってきた。その頃、学会では他宗教や他宗派のことを「邪教・邪宗」と呼んでいた。当時は邪教・邪宗に対して嫌悪感を抱くのが正しい学会員のあり方なのだという空気さえあった。
そんな私には、1993年、小学校6年生の時の修学旅行での忘れられない思い出がある。旅行先は日光だった。私は両親の教えを忠実に守り、その地の神社や寺で手を合わせるといった宗教的行為はしなかった。母親からは「社寺にいる間はずっと南無妙法蓮華経(=学会員が日常的な宗教儀式などで唱えるフレーズ)と心の中で唱え続けなさい」と言われていたので、それも実践した。
だが、旅行の最後の最後で私は大失態を犯してしまう。
土産の「ダルマ人形」で母親は頭痛に
私は親を喜ばせようと土産を買った。購入したのはダルマを模した人形だった。「お母さん、喜んでくれるかなあ」と、小学生らしい心持ちで。
ところが家に帰ると母の様子がおかしい。「どうしたの?」と聞くと、朝から頭痛がするのだという。心配しつつ、私は母に贈り物でもするかのように「じゃーん!」とダルマ人形を披露した。母の形相が変わった。
「朝から頭が痛かったのは、この人形のせいだったのね! こんな邪宗のダルマをあなたが買ったから私がこんな目に遭っているのよ!」
そう激高しながら母はダルマの人形をごみ箱に捨ててしまった。当時、私の中には「ダルマ=邪宗の祖」という認識はなかった。だから土産に選んだのだが、子どもながらにショックだった。部屋に駆け込み、ひとり泣いた記憶が今でも残っている。
こうした経験をした「創価学会2世」は我が家に限ったものではない。私と同じ2世の友人は「邪宗」の寺で購入した財布を土産に持ち帰ったところ、やはり母親が激高し、財布を奪い取るやいなや庭で燃やしてしまったという。彼のショックはいかばかりだったか・・・・・・。
創価学会はもともと日蓮正宗という日蓮系宗派の信徒団体の1つで、基本的に日蓮正宗の教えに基づいていた。そんな日蓮正宗は、たとえば「四箇の格言」と呼ばれる、他宗批判を象徴する言葉を重んじる。四箇の格言とは「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」という4つのフレーズのことで、日蓮が生きていた時代の代表的な他宗教の悪性を突いた言葉である。
この格言に込められた他宗批判の思想は創価学会の布教におけるバイブル的な著作『折伏教典』にも余すところなく反映されており、そこでは「これでもか」というくらい苛烈な他宗批判が詳述されている。創価学会が右肩上がりで成長していた昭和の時代、学会員たちは『折伏教典』を片手に布教活動に出かけては「邪宗」を破折(=くじき破ること)して歩いた。この頃、日蓮正宗(と創価学会)以外の宗教はすべて邪宗・邪教だと位置づけられていたのである。
しかし時代が平成に変わる頃、こうした傾向に変化が訪れる。
学会員に変化をもたらした2つもの
学会員たちに変化をもたらしたものは大きく2つある。
1つは、教団のカリスマリーダー池田大作氏である。池田氏は昭和の時代から他宗教、他宗派の著名人たちと対話を重ねてきていた。そこには相手を破折しようなどという姿勢は見られない。この池田氏の姿勢は、学会員たちに「他宗教、他宗派の人たちを一概に邪教の徒として斬って捨てるのではなく、それらの人たちとの間に理解の架け橋をかけることもアリなのか」という揺らぎをもたらした。
もう1つが、1991年に創価学会が日蓮正宗とたもとを分かったことだ。ここから「すべての他宗教、他宗派は邪教・邪宗」という創価学会内の常識は変わりはじめた。先に述べた通り、学会の攻撃性は日蓮正宗と歩調を合わせていたがために生まれた部分が大きいからだ。日蓮正宗と別れたことで学会は他宗教、他宗派に対するスタンスを自らの裁量で決められるようになった。
学会はこの後、地域貢献などにも打って出るようになる。社会との接点が増えるに連れて学会内の常識、学会員たちの態度も変わっていったのだ。
こうして他宗教、他宗派への態度は軟化していった。学会員たちの間で「邪教・邪宗」は次第に「他宗」へと言い換えられるようになった。
先の「ダルマ事件」が起きた1993年という年は、創価学会が日蓮正宗とたもとを分かってまだ間もない時期。学会員たちの意識、常識はまだ大きくは変わっていなかったのだろうと思われる。
平成の約30年間で創価学会は間違いなく変化を遂げた。では、この教団が持っていた排他性や攻撃性は完全に消え去ったのだろうか。
令和の時代の創価学会の他宗教・他宗派へのスタンスをかいつまんで例示すれば、個人の信仰として「鳥居をくぐらない」といった判断をする人は少数ながらいる。しかし、みなが「鳥居をくぐるな」と指導したり、されたりといった情景はなくなった。かつては非難の対象だった「お祭りの神輿をかつぐ」「神社仏閣めぐりをする」といったことも今では問題視されなくなっている。
背景には、やはり、先に触れた地域貢献重視の姿勢に転じたことがある。地元の自治会や消防団などに積極的にかかわるようになったことも影響している。「神輿をかつぐ」のは地域貢献の一環だからだ。今では地域の祭りのために教団の会館を貸し出すといった事例まである。
創価学会の「他宗教・他宗派に排他的で攻撃的」という側面は相当程度、薄れてきたといえる。少なくとも、かつてのように「東の立正佼成会、西の天理教」と「敵」を排撃するような態度を見せることはなくなった。
「仮想敵」を必要としてきた歴史
一方、学会が「敵」だと認定した相手については現在も苛烈に攻撃する。わかりやすい例が「共産党攻撃」だ。たもとを分かった日蓮正宗に対してもそうである。
創価学会の重要な行事に「本部幹部会」がある。幹部会では青年部のリーダーたちが「敵」を責めたてるスピーチを行い、多くの学会員が衛星中継を通じた放映でそれを何度も視聴する。そこで幹部たちが語る「敵」は、会内ではしばしば「仏敵(ぶってき)」と表現される。
長年、創価学会で信仰活動をし、学会の歴史について詳細に学んできた私からすれば、創価学会はいつの時代においても「仮想敵」を必要としてきたように見える。「敵」を作ることは教団の結束に繋がるからだ。その意味で創価学会の排他性、攻撃性は令和のこの時代にも組織文化として残っている。
私が気になっているのは今後だ。学会は、根強く残る排他性や攻撃性を克服しようと努力できるだろうか(そもそもそんな努力は必要ないという理論を堅持する可能性はある)。個人的には、敵を作り、そこに攻撃を行うことで団結を促そうとするやり方は、長期的には組織のためにならないと思っている。
いま、旧統一教会の問題が話題だ。同教団が自分たちを特別視し、選民思想的に振る舞うがゆえに排他的・攻撃的になっている姿は多くの人の知るところとなった。詳述はしないが、創価学会の攻撃性の源は旧統一教会のそれとは異なる。
だが、排他性・攻撃性が「独善」を生み、「自分たちこそが正しい」という強い信念が、たとえば外部からの貴重な意見に耳を傾ける姿勢を失わせるということがある。国であれ、企業であれ、宗教団体であれ、外部の意見を受け付けない組織が誤った方向へ向かってしまうのは歴史の常である。
旧統一教会問題がフォーカスされている今こそ、創価学会には自らの内に宿る排他性や攻撃性を直視し、再考してほしいと思う。そのうえで「歴史の常」にからめ取られない宗教組織の模範を示してほしいと願っている。