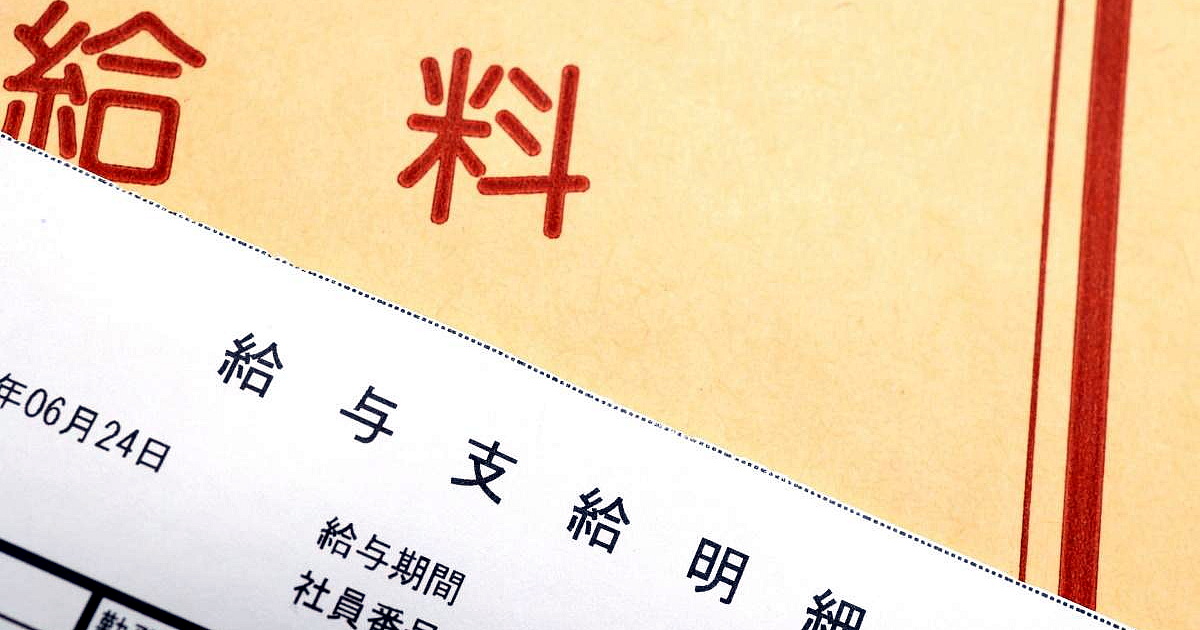国が動けば「給与」は簡単に上がるワケ、労働者を苦しめるだけの“政府の怠慢”とは?(Fin Tech Journal 2023/10/10 掲載)
日本の賃金がなかなか上昇しない。岸田政権は経済対策を通じて賃上げ実現に取り組むとしているが、どの程度の成果が得られるのか現状では不透明だ。政権も含めて、賃上げを実現するのは難しいと思っている人も多いかもしれないが、実は手っ取り早く賃金を上げる方法がある。
執筆:経済評論家 加谷珪一
賃金は基本的に付加価値に比例する
経済学的に考えると、賃金というのは企業収益に比例して上昇する。もう少し厳密に言えば企業が生み出した付加価値に比例して上がっていく。逆に言えば、企業の収益が拡大していない状態では、賃金は上がりようがない。日本企業全体の実質的な売上高は過去30年、ほぼ横ばいに近い状態で推移しており、これは世界的にみてかなりの異常事態である。だが日本企業の利益は継続的に上昇しているという現実を考えると、企業はコストカットを続けることで利益を捻出してきたと解釈できる。
売上高が伸びない中で、利益を増やそうとすればコストカット以外に方法はなく、人件費はその安易な対象となってきた。
企業側の理屈としては収益が拡大していない以上、賃金は上げようがないという話になるのだが、低収益を放置してきたのはその企業に他ならず、最終的には企業経営のあり方が低賃金の根本原因と考えて良い。
状況を改善するには 企業の収益を抜本的に変えていく必要があり、こうした政策を実現するには相応の手間や時間がかかる。しかしながら、一定程度であれば、即効性のある形で賃金を引き上げる方法が残されている。それは、あっけないほど簡単な話だが、政府が法の執行を適正に実施するというものである。
日本の場合、中小企業は大企業の隷属的な下請けになっているケースが多い。大企業が過度な買い叩きを行ったり、十分な対価を支払わない状況が続くと、中小企業の収益はいつまで経っても改善しない。実際、日本の中小企業の利益率は圧倒的に大企業より低くなっており、欧米各国とは状況が大きく差が付いている。
日本の中小企業の利益率が異常に低い理由
欧米各国における中小企業の営業利益率は6~9%程度と大企業と大差ない水準となっているが、日本は2%程度と著しく低い。日本の中小企業が独自で顧客を開拓できておらず、大企業から買い叩かれている状況が推察できる数字だ。
大企業が中小企業に対して過度に買い叩きを行うといった行為は法律で禁止されており、本来であれば、中小企業も一定水準以上の利益を確保できる。ところが日本の場合、一連の行為に対しては、企業活動優先の観点から、ある種のお目こぼしが行われており、十分に法が執行されてこなかった。
昭和の高度成長期ならいざ知らず、現代においても中小零細企業への過度な買い叩き行為はあちこちで散見される。こうした状況から中小企業を守るために下請け法、独占禁止法といった法律が存在していることを考えれば、政府は既存の法体系に基づき、適正に法を執行したり、行政指導を行う義務がある。
もっとも、法の的確な執行によって取引先を安易に買い叩けないとなれば、企業は労働者の賃金を減らす可能性もある。だが日本には欧米各国と同レベルの労働法制が存在しており、労働者に対する無制限の残業や、過度な低賃金労働も禁止されている。
ちなみに労働者の雇用環境や賃金については、独占禁止法などと同様、企業活動優先ということで、労働基準局が十分にその権限を行使してこなかったのが現実である。
日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせることは違法だったが、これには例外規定が存在しており、法律の条文は事実上無効化されていた。その例外規定とは、企業と労働者が協定を結んだ場合に限り、法定労働時間を超えて仕事をさせることができるという、いわゆる「36協定」である。
だが、36協定についても、働き方改革関連法の成立によって、残業時間の上限規制が厳しく設定されるようになり、労働者を会社都合で好き放題働かせることは不可能となっている。後は政府が、法律を遵守しない企業をどれだけ適切に指導できるのかにかかっている。
政府が本当にやるべきこと
これらの法律を適正に運用するだけで、企業は下請けを買い叩いたり、コスト増を労働者に負担させるといった行為ができなくなる。必然的に経営者は、自社が生み出す付加価値を大きくするという、企業としては当然の改革を実施するようになり、それに伴って賃金は上昇していく。
従来の日本社会では、経済状況が厳しくなると企業を支援するような政策ばかり実施してきた。だが、企業というのは、自ら積極的にリスクを取り、競争環境の中で収益拡大を目指すべき存在であり、本当に保護すべきは労働者の側である。
仮に労働者が失業しても、十分な失業保険と再就職の支援を得られるのであれば、労働者は安心して働くことができる。低賃金で労働者を酷使する企業は必然的に市場からの退出を迫られ、企業の付加価値は増大していく。こうした状況になって困るのは、現状維持を望み、適切な競争を忌避する一部の経営者だけだろう。
日本の支援策は、この重要な部分を履き違えている面が多分にあり、労働者の雇用を守るという名のもとに、経営努力をしない企業を延命させる政策ばかり実施してきた。結果として低賃金の慢性化を招いてきたとも言えるだろう。
こうしたミクロな政策の話をすると、細かいことを議論しても意味がないと言った批判の声が寄せられるのだが、こうした現実から目を背ける態度こそが、日本経済の長期停滞を招いている。企業が十分な競争環境に置かれず、収益拡大のインセンティブが働かない状況では、いくら財政出動などを行っても、状況を悪化させるだけである。
岸田政権、秋の臨時国会の注目ポイント
岸田政権は秋の臨時国会で大型の経済対策を予定しているが、従来と同じ単純な企業支援策にとどまった場合、日本経済の状況を抜本的に好転させることは難しい。政権が掲げた五本柱の中には、デジタル化や物流システムの改善など、中長期的な企業経営の改革プランが含まれているほか、買い叩き行為の是正といった法執行に関する項目もある。
問題は、票につながらない、こうした地味な項目に対してどれだけリソースを割けるのかという部分である。繰り返しになるが、一連の法体系の執行を普通に実施するだけで、経営の改革や組織の再編は一定程度、進む。政府は原点に戻り、すでに存在している法律をしっかりと適用する基本政策を実施することに力を注ぐべきであり、これこそが即効性のある賃上げ策となるはずだ。
◇
加谷珪一(かや・けいいち) 経済評論家
1969年宮城県仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。 野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『億万長者への道は経済学に書いてある』(クロスメディア・パブリッシング)、『感じる経済学』(SBクリエイティブ)、『ポスト新産業革命』(CCCメディアハウス)、『新富裕層の研究-日本経済を変える新たな仕組み』(祥伝社新書)、『教養として身につけておきたい 戦争と経済の本質』(総合法令出版)などがある。