 科学・技術
科学・技術 上位論文数、世界12位に 初めて10位以内に入らず 自然科学分野
世界で2018~20年に発表された自然科学分野で影響力の大きな上位論文数で、日本が世界12位と、統計がある1981年以降、初めて10位以内から脱落した。日本は研究力の低迷に歯止めがかかっていない。
 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術 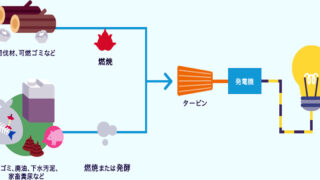 科学・技術
科学・技術 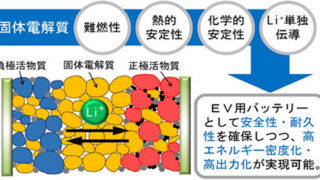 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術 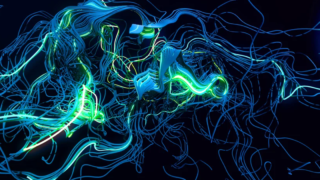 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術 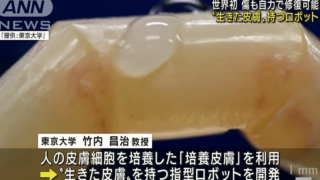 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術