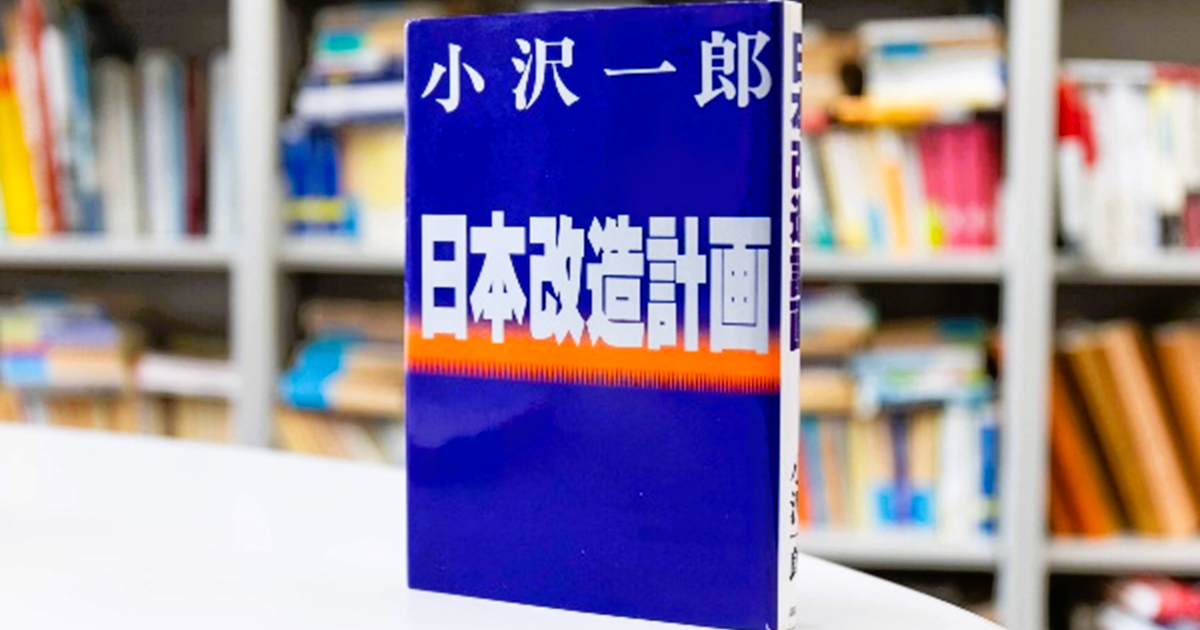日本の政治に絶望している人に読んでほしい本
小沢一郎『日本改造計画』 今こそ読みたい日本改革構想(日経 BOOK PLUS 2024.5.29)
牧原 出/東京大学先端科学技術研究センター教授
政治学者で東京大学先端科学技術研究センター教授の牧原出さんが選ぶ、「日本の政治に絶望している人に読んでほしい本」2回目は、マックス・ヴェーバーの『職業としての政治』と小沢一郎の『日本改造計画』を紹介する。『職業としての政治』は学生の前で政治家に必要な資質を熱く語った講演録。『日本改造計画』は冷戦後の我が国の改革構想を、学者を中心とした研究会をもとに小沢自身が執筆したもの。いずれも今こそ読んでおきたい本だ。
必要なのは「情熱」「責任感」「判断力」
第1回「 坂口恭平は『現代の福沢諭吉』 政治不信の中で読みたい本 」は広い意味で政治について考え、実践してきた人物の本を紹介しました。第2回はマックス・ヴェーバーによる「政治家論」とプロフェッショナルな政治家による「政策構想の本」を紹介します。
まず、紹介するのはドイツの社会学者であり、政治学者、経済史・経済学者であるマックス・ヴェーバーの『 職業としての政治 』(脇圭平訳/岩波文庫)です。本書に収められているのは、第1次世界大戦でドイツが敗戦した直後、ヴェーバーが学生たちに向けて「政治とは何か」を問いかけた講演録です。
第1次世界大戦末期のドイツでは兵士と労働者が蜂起、皇帝はオランダに亡命し、ドイツ共和国が樹立されました。革命運動が各地に広がる一方で、反革命派との争いも激化し、国内は混沌(こんとん)とした状態でした。そんな中で行われた講演で、ヴェーバーは「政治家には情熱、責任感、判断力という3つの資質が特に重要である」と説きました。
さらには、
政治への献身は情熱からのみ生まれ、情熱によってのみ培われる。
政治家は自分の内部に巣くう虚栄心を克服せねばならない。
政治とは、情熱と判断力の2つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である。
どんな事態に直面しても「それにもかかわらず!」と言い切る自信のある人間。そういう人間だけが政治への「天職」を持つ。
──とも述べています。
この講演はヴェーバーが亡くなる前年に行われましたが、「語り」の強さを感じることができます。社会の秩序が崩れ、国を再興しなければならないとき、政治家はどうあるべきか、今だからこそヴェーバーの言葉は心に響くと思います。
冷戦後日本をどう変えるべきか
日本はどう変わるべきか。そのヒントになるのが『日本改造計画』(小沢一郎著/講談社)です。
1989年のベルリンの壁崩壊によって東西冷戦は終結しました。冷戦という国際環境の下で作られた戦後日本をどう変えていくべきか。小沢は冷戦終結を明治維新、第2次世界大戦に続く変革期と捉え、日本を「普通の国」にするための「第3の改革」を訴えました。
本書が刊行されたのは1993年5月。小沢は同年6月に自民党を離党して新生党を立ち上げ、8月には細川護熙(もりひろ)連立内閣を成立させました。『月刊正論』(2023年7月号/産経新聞)では、講談社の豊田利男さんらが本書の制作過程を回想しています。執筆の協力者として北岡伸一さん、御厨貴さんら多数の学者がかかわりました。しかし、小沢は本書のための研究会で議論を重ね、自ら加筆・修正したとのことなので、小沢本人の著書といえるでしょう。
話題になった「自己責任論」
本書には当時大きな話題になった、米国のグランド・キャニオンについての記述があります。高低差約1200メートルのグランド・キャニオンには転落を防ぐ柵がありません。転落事故は「自己責任」だからです。これが日本だったら「なぜ柵を設置し、安全策を講じなかったのか」と管理責任者は非難を浴びます。
米国人は自分で自分の身を守ろうとするのに対し、日本人は自分の身さえ国や規制によって守ってもらおうとする。だから、小沢は日本人には「自己責任」、地方には「自立」、政治では同調圧力に負けない「強いリーダーシップ」が大事だと説き、大久保利通、伊藤博文、原敬、吉田茂といったリーダーの名前を挙げます。
本書では冷戦後の安全保障に触れています。米国に守られた「特殊な国」から「普通の国」になるべきだと主張します。有事に米軍に協力する集団的自衛権ではなく、国連軍に自衛隊が協力する集団安全保障の立場を取るという考え方で、それはその後のPKO(平和維持活動)の自衛隊派遣にもつながりました。
また、地方分権についても書かれています。「全国を300の市にするべきだ」という主張は、その後、平成の市町村大合併が行われたことを思うと、かなり斬新でした。
おそらく小沢は自らの師である田中角栄の『 日本列島改造論 』(日刊工業新聞社)を意識して、本書を書いたのでしょう。政治家として日本の将来をしっかりと見据えよう、新しい日本の政治ビジョンをきちんと作り上げようという気迫が伝わります。その背後には、冷戦終結後、世界中で起きた改革の波がありました。単に社会主義国が崩壊しただけでなく、諸外国でも、例えば司法権の強化、憲法における人権擁護の強化、地方分権化、さまざまな民主化や透明化の動きがありました。
最近の政治家は声を上げようとしませんし、まともな本すら書きません。今こそ識者を集めて研究会を開き、これからの日本をどうするか真剣に議論すべきだと思うのですが。
文/三浦香代子 構成/桜井保幸(日経BOOKプラス編集) 写真
◇
牧原 出(まきはら いづる)
東京大学先端科学技術研究センター教授
1967年、愛知県生まれ。専門は行政学。東京大学法学部を卒業後、東北大学法学部助教授、同大学大学院法学研究科教授等を経て、2013年4月より東京大学先端科学技術研究センター教授。著書に『内閣政治と「大蔵省支配」 政治主導の条件』『行政改革と調整のシステム』『権力移行 何が政治を安定させるのか』『「安倍一強」の謎』『崩れる政治を立て直す 21世紀の日本行政改革論』『田中耕太郎 闘う司法の確立者、世界法の探究者』など。