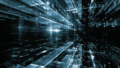富士山が噴火したら…首都圏はどうなる? 元国立極地研究所所長・島村英紀氏が解く(日刊ゲンダイ 公開日:2025/06/30 06:00 更新日:2025/06/30 06:00)
富士山は江戸時代の1707年(宝永の大噴火)を最後に噴火していない。当時の記録によれば、南東部の中腹から噴煙が上がって、2時間ほどで江戸に降灰があったという。いつ起こってもおかしくないといわれるが、どんな被害が想定されるのだろか。歴史的文献には当時の記録が残されているという。「火山入門—日本誕生から破局噴火まで」の著者で、元国立極地研究所所長の島村英紀氏(火山学)にまとめてもらった。
◇ ◇ ◇
平安時代には、毎年のように山頂噴火があったことが記録されている。富士山の三大噴火のうち800~802(延暦19~21)年に起きた平安時代の「延暦の噴火」についての文献は『日本紀略』などを除いてほとんどない。この『日本紀略』には降灰が多い爆発的な噴火だったことや、東海道の本道である足柄峠越えの道が火山礫が積もって通行困難となったため、新たに箱根路を開いたとある。街道を付け替えなければならないほどの噴火ならば大噴火にちがいない、というのが三大噴火のひとつとして数えられた根拠になっていた。
記録最後の宝永噴火では、噴煙は15000~20000メートルにも昇ったとされる。成層圏の高さだ。そして火山灰は上空の偏西風に乗っていまの首都圏に10~30センチも積もった。とくにいまの神奈川県には多かった。
■噴火は16日間続き、東京には噴煙が……
また、江戸城など江戸の中心部にいた旗本・政治家・学者でもあった新井白石は自叙伝『折たく柴の記』で、『はじめに白い火山灰が雪のように降り、やがて黒い火山灰に変わった』ことを記している。降りしきる灰のために、江戸では昼間でも燭台に明かりを灯さねばならないほど暗くなっていたことも書かれている。
白石が記録したように江戸で降った火山灰が途中で変化したのは、最初は二酸化ケイ素を多く含んだ白っぽい火山灰、数時間後には、二酸化ケイ素が少なく黒っぽい火山灰に変わったからである。前述のように、白っぽい軽石や火山灰は密度が小さいデイサイトマグマから、そしてスコリアや黒っぽい火山灰は、密度が大きい安山岩マグマから出来ていた。
噴火は16日間続いたが、江戸では火山灰が断続的に降り続いた。ときには黒い大粒の火山灰が降りしきって、家々の屋根に落ちる音が大雨のようだったという。このとき江戸市中に降りつもった火山灰は、その後も強い風が吹くと飛散したために、市民は富士山の噴火後も長期にわたって呼吸器疾患に悩まされた。
富士山が300年間噴火しないことは非常に珍しく、その後の噴火が非常に大きいことを意味するといえる。富士山の噴火については、東南海地震の49日後に噴火した例もあるからトラフ地震が迫って来ている今は連動も考えていたほうがいい。
◇ ◇ ◇