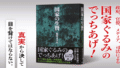革命におびえるランドパワー 中国やロシアが高圧的な理由(日本経済新聞 2025年11月23日 10:00 [会員限定記事])
地政学まずはコレだけ㉖ 編集委員 田中孝幸
10代の学生からビジネスパーソン、高齢者まで幅広い世代の読者から寄せられた質問に答え、地政学の視点から国際情勢を読み解きます。
なぜ中国やロシアは、日本など各国に高圧的な姿勢をみせるのですか。
A 内政の余裕のなさが背景にあります。
地政学上、広大な国土と多くの人口、長大な陸上国境を持つ大陸国家はランドパワーと呼ばれます。ロシアや中国がその典型です。
ランドパワーの特徴の一つに、民主化のハードルが高いことが挙げられます。陸続きの周辺勢力と戦乱を繰り返した結果、大陸国家は国内に多数の民族や宗教、言語を抱えます。少数民族の数は中国で55、ロシアは100以上にのぼります。

分裂への遠心力が強い国では秩序維持が最優先され、市民的権利や自由は後回しにされがちです。民族間で共通の基盤が少ない中で政治的自由を許せば混乱に陥り、内乱などを引き起こすという危機感が背景にあります。
こうした非民主的な国々のリーダーは、政変におびえている点で共通します。公正な選挙がない国の政権交代は革命を意味し、前体制の指導者は投獄や死が避けられないためです。内外が敵だらけという強迫観念を強め、国内では市民への抑圧に、対外的には強硬路線に走る結果をもたらします。
権威主義国家では、主に政権内の不透明な権力闘争を通じて人事が決まります。トップの顔色をうかがって失点を避ける役人が権力の階段を上るシステムともいえます。
外交官も保身に追われるあまり、本国向けのアピールのために他国への居丈高な言動で同僚と競うケースが少なくありません。台湾有事を巡る高市早苗首相の答弁に対する薛剣・駐大阪総領事の過激なSNS投稿もその一例とみられます。
そもそも軍や治安機関が幅をきかせる中ロでは政権内での外務省の序列は高くなく、余裕のない立場にあります。過去に高圧的な姿勢で知られたロシア外務省の元幹部も「他国への失礼な態度は国益を損ねることは分かっていたが、生き残るにはやむをえなかった」と語っています。
日本はそうした国々にどう対処すべきでしょうか。
A 冷静さを失わず、相手に重視される力を持つことが重要です。
強い不安や不信に陥った国と信頼関係を築くのは困難です。こうした国々は外交活動や民間の国際交流も、他国を出し抜こうとする謀略や工作活動の一環だとみなす傾向があります。
中国では2014年の「反スパイ法」施行以降、少なくとも17人の邦人が拘束されました。日本政府は不透明な司法プロセスに抗議していますが、中国側の態度に変化はみられません。中国の国家安全省は19日、「日本情報機関による中国への浸透・機密窃取のスパイ事件を数多く摘発してきた」と一方的に主張しました。
ロシアの西側諸国への不信感は決定的です。ウクライナへの殺傷性のある武器提供を控えている日本に対しても11日、日本人30人を無期限の入国禁止にする制裁を発表しました。対象にはロシア関連の報道に携わってきた記者も含まれました。
結局、こうした権威主義国家に通じる最も効果的な言語は、国際社会での力関係だといえます。日本にとって世界最強の軍を持つ米国との同盟関係が最も重要なのは、周囲の権威主義国家もその強度を極めて重視しているためです。
中国は右派色が強い高市首相を警戒し、就任時の習近平(シー・ジンピン)国家主席の祝電送付を見送りました。高市首相が10月末に訪日したトランプ米大統領との関係強化を誇示すると、ほどなく習氏は訪問先の韓国・慶州で高市首相との初会談に応じました。
中国は台湾有事に関する高市首相の国会答弁を受け、日本への圧力を強めています。一方、グラス駐日米大使は20日、X(旧ツイッター)への投稿で「威圧的な手段に訴えるのは中国政府にとって断ち難い悪癖のようだ」と批判し、日本への支持を重ねて表明しました。
中国側は今後、トランプ大統領らの出方を踏まえて、日本への圧力の強弱を判断することになりそうです。
田中孝幸(たなか・たかゆき)
1998年日本経済新聞社入社。政治部、経済部、国際部を経てモスクワ支局員、ウィーン支局長など歴任。現在、編集委員兼論説委員。著書「13歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海」で八重洲本大賞、ビジネス書グランプリ2023・リベラルアーツ部門賞など受賞。