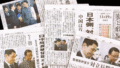ビル・ゲイツが気候変動の絶対視をやめるに到った「3つの重い真実」…脱炭素一辺倒の世界潮流に大逆転は起きるのか(現代ビジネス 2025.11.18)
朝香 豊 経済評論家
1964年、愛知県生まれ。私立東海中学、東海高校を経て、早稲田大学法学部卒。経済評論家。日本のバブル崩壊とサブプライムローン危機・リーマンショックを事前に予測し、的中させた。ブログ「日本再興ニュース」(https://nippon-saikou.com)は、冷静な視点で展開される記事が好評である。近著に『左翼を心の底から懺悔させる本』(取り扱いはアマゾンのみ)がある。
ビル・ゲイツの転換
マイクロソフトの共同創業者であるビル・ゲイツ氏は、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などを通じて、貧困の解消、疾病の撲滅、気候変動の抑制などに取り組んできたことが知られている。彼は気候変動の抑制は最重要課題だとの立場から、これまで脱二酸化炭素の旗振り役をやってきたが、先頃従来の路線を大きく転換する論文を発表して、話題になった。
その論文は「気候に関する3つの重い真実」というものだ。

ゲイツ氏が語る重い真実の1つ目は、「気候変動は重大な問題であるが、文明の終わりにはならない」というものだ。気候変動については、気温が上昇することで将来の人類がこの地上で暮らせなくなるから、もはや待ったなしだというような、やたら危機を煽る主張が広くなされてきたが、ゲイツ氏はそんな酷いことにはならないぞと、言い出したのだ。
それどころかゲイツ氏は、「生活改善という視点で見れば、より多くのエネルギーを使うのはいいことだ」「より多くのエネルギー消費は繁栄の鍵となる」とまで言い、貧困国と先進国との間では一人当たり50倍にも達するエネルギー使用量の格差があることを、グラフで示すようなことまで行った。
ゲイツ氏は貧困の解消も重要な問題であり、そのために貧困層のエネルギー使用量はもっと増えるべきではないのか、脱炭素を前提にした上で貧困の解消を実現するのは、今の技術レベルではまだ難しいのではないか、もっと技術が改善されるのを待つべきではないのかと伝えている。
ゲイツ氏はAIが進展する中で、技術改善が今後急速に進むことには楽観的な見方も見せてはいる。
それでも、もっとエネルギーを使って経済成長を促した方がいいというのは、環境絶対派の人たちからしたら、「裏切り」だということになるだろう。
人類の進歩を図る指標とは
ゲイツ氏が語る重い真実の2つ目は、「気温は気候問題についての進歩を測る最善の指標にはならない」というものだ。ただし、ゲイツ氏の実際の主張を読むと、このまとめ方はちょっと違っているのではないかと思う。私は彼の主張のまとめであるなら「気温にフォーカスすることは、人類の進歩を測る最善の指標にはならない」と言った方がいいとの考えだ。
ゲイツ氏が言いたいのは、化石燃料を燃やして気温上昇につながることは悪だという立場を絶対視するのは不適切ではないかというものだ。
地下に眠る化石燃料を掘り出せば、生活改善が大いに進むことがわかっている貧しい発展途上国があるとしよう。この場合に化石燃料を掘り出せるようにして、貧困問題に対処する方が正しいのではないかというのが、ゲイツ氏の考えだ。
ところが脱二酸化炭素を絶対視する側からは、例えば国際的な金融機関に「グラスゴー金融同盟」への加入を促して、化石燃料の掘り出しへの資金提供を行えないようにするなど、こうした資源開発を進ませない動きが展開された。
「グラスゴー金融同盟」とは、2050年までに温暖化ガス排出量の実質ゼロを目指す金融機関の集まりだが、入らないといけない空気が醸成されて、世界的な金融機関がこぞって加入する状態になった。ただ脱二酸化炭素に否定的なトランプ氏が大統領選挙で勝利したことをきっかけとして、昨年秋以降は脱退する金融機関が相次いでいる。
それはともかく、こうした締め付けによって化石燃料を開発するのに必要な資金提供が行われなければ、現地の人たちの貧しい暮らしが改善されないことになる。地下資源を掘り出すようにして、現地で雇用を作り出し、現地の人たちにお金が落ちるようになれば、今は貧困に喘いでいる現地の人たちの生活を改善することができるのに、それは問題ではないかと、ゲイツ氏は語っているのだ。
現地の人たちの貧しい暮らしが改善されない問題は気候問題ではなく、人々の生活が改善されないという生活の質の問題だ。この論調に従うとすれば、真実の2つ目は「気温は気候問題についての進歩を測る最善の指標にはならない」というよりも、「気温にフォーカスすることは、人類の進歩を測る最善の指標にはならない」といった方がより適切なのではないかというのが、私の考えだ。
経済成長こそが
ゲイツ氏が語る重い真実の3つ目は、「健康と繁栄が気候変動に対する最高の防御だ」というものだ。
これまでは、気候変動をこのまま放置すると、気候変動が原因で死亡する人がどんどん増えていくことになるとして、危機を煽る論調が広がっていた。
ところがゲイツ氏は、シカゴ大学の研究成果に基づき、低所得国がこれまでのような経済成長を続ければ、今世紀末においての気候変動による死亡者数は半分以下にまで下がるとの予測結果を引っ張り出してきた。
経済成長して、人々の生活環境が改善し、公衆衛生もよくなれば、人々が安易に死ぬことはなくなる。
環境絶対主義の立場からは、気候変動が激しくなれば、激しい豪雨によって洪水に苦しむことになるから、それは問題だと主張される。だが、豪雨が降ってもしっかりとした堤防を築けば、生活圏を守ることができることになる。ならば堤防を築くことができる豊かさを経済成長によって実現すればいいのではないのか。
ゲイツ氏からすれば、貧困の解消や疾病の撲滅も、気候変動の抑制と並ぶ重要な課題なのだ。
ゲイツ氏は乳幼児を中心にワクチン接種を押し広げ、乳幼児の死亡率を引き下げる活動を展開しているが、広範囲なワクチン接種ができるのも、それが実現できる経済力あってのことだ。だったらより速く、より広範囲の経済成長を目指すべきではないのか。これがゲイツ氏の主張だ。
科学技術の進歩とその普及は、低所得国の暮らしぶりを改善するのに大いに役立っている。ゲイツ氏は一例として、低所得国でもスマホを持つ人が増える中で起こる変化を持ち出した。
人々がスマホを持つようになった結果、自分たちの農地で、何をどの時期に植え、どのように育てれば、収入を効率的に増やせるかがわかるようになったというのだ。
また、テクノロジーの進歩によって、乾燥地帯で生育させるのに適した品種開発なんかも、ものすごく進んでいるという例も挙げた。
科学技術の進展に、もっと信頼を
このゲイツ氏の論文には出ていないが、実は鳥取大学の乾燥地研究センターが、こういう研究で素晴らしい成果を生み出しているのは、日本人として知っておきたい。
一般に小麦は冷涼で、やや乾燥している土地が栽培に適しているとされている。サハラ砂漠はとてもではないが冷涼ではないから、小麦の栽培には向いていないだろう。小麦が乾燥地帯の方が適していると言っても、さすがにサハラ砂漠は乾燥しすぎで、栽培には向いていないということになるだろう。普通に考えれば、こんなところで小麦が育つわけがないと考えるのが普通だ。
ところが鳥取大学は、遺伝子組み換え技術を駆使して、サハラ砂漠でも栽培できる小麦を開発している。
アフリカのスーダンは国土の大半がサハラ砂漠の国としても知られているが、ここで鳥取大学が開発した小麦が青々と育っているのだ。
こうした従来の常識を超える科学技術の進展がありうることに、もっと信頼を持つべきではないのか。経済成長を実現し、科学技術が発展すれば、温暖化そのものを抑え込める可能性が広がるだけでなく、温暖化が進んだ場合の対処能力も大いに高めることができるんじゃないか。これがゲイツ氏の主張だ。
ついに軌道修正の流れが
人為的な二酸化炭素の放出によって地球温暖化が進んでいて、そのことは重大な問題であるという主張を、ゲイツ氏は建前としては変えたわけではない。
だが、そこから先の、何を優先的に進めるべきかの主張は完全に変わった。
温暖化の問題に直接フォーカスするよりも、経済成長を追求することの方がもっと大切なのではないか。経済成長が実現できるなら、貧困問題を解消し、気候変動に対処できる力を高めることができるのではないか。経済成長により科学技術がさらに進化し、気候変動問題に対処する技術も進んでいくことになるのではないか。だから経済成長を犠牲にしてでも温暖化の問題に直接フォーカスするというアプローチよりも、経済成長によって人間の持つ科学技術を発展させる可能性をもっと信じようではないか。科学技術を発展させれば温暖化対策も進むようになるのではないかというのが、ゲイツ氏の主張だ。
人為的な二酸化炭素放出が地球温暖化を引き起こしているという議論には懐疑的な立場の人も多い。だから人為的な二酸化炭素放出が地球温暖化を引き起こしていると考えるかどうかという表面部分だけを取り出せば、こうした人たちとゲイツ氏の考えは対立関係にあるということになるだろう。
だが、ゲイツ氏の主張は、温暖化の問題を絶対視しないで、私たちが経済成長を重視し、科学技術を発展させ、より豊かになることこそが、問題を解決する鍵になるというものだから、この結論からすれば、懐疑派の人たちとゲイツ氏の考えは、実質的には違いはないということになる。
さて、太陽光発電、風力発電、電気自動車といった分野で、今や中国の圧倒的な優位が確立している。この中で中国にやられっぱなしにならないために、西側で軌道修正が図られていく流れが出てくることになっていくと、私は以前から予想していた。
この位置付けの中で今回のゲイツ氏の論文に着目したい。この流れは今後徐々に広がっていくことになるだろう。時代は大きな変わり目を迎えたのではないか。