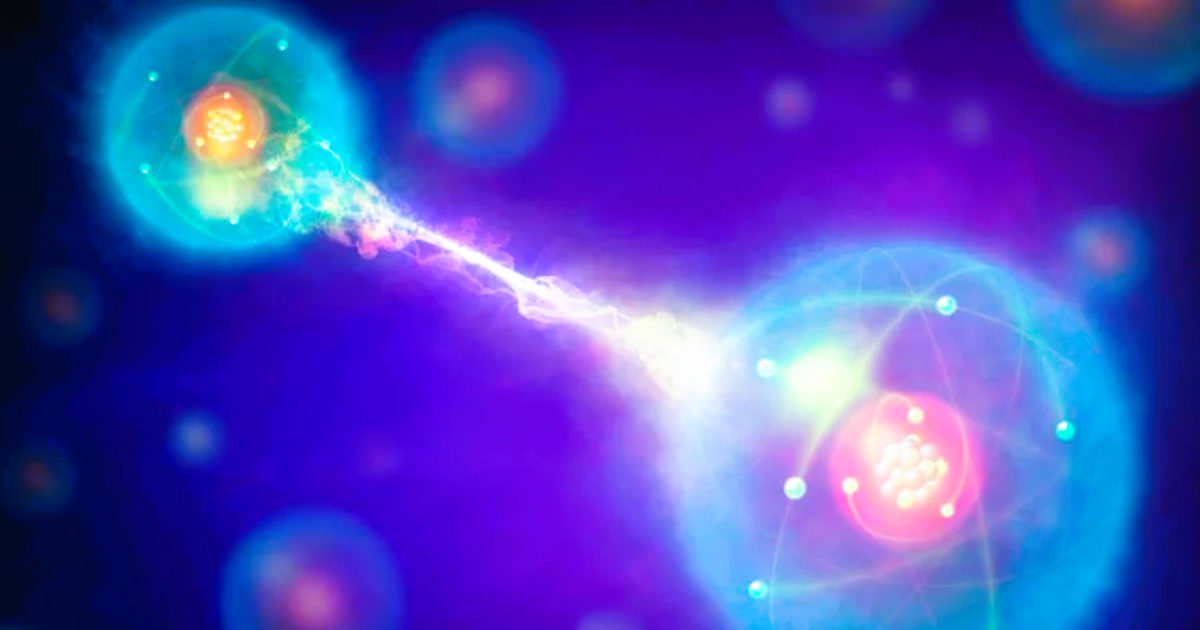みんな大好き「多世界解釈」が危機を迎えている:理論的な大黒柱が崩壊(ナゾロジー 2025.01.14 17:00:02 Tuesday)
皆さんは「もしもあのとき違う選択をしていたら、今ごろどうなっていただろう?」と考えたことはありませんか。
人間は誰しも、日常生活の中で小さなターニングポイントをいくつも迎えます。
たとえば、今この瞬間、この文章を読んでいる“あなた”とはほんの少しだけ違う行動や選択をしている“もうひとりのあなた”が、見えない別の世界に同時に存在している──そんな奇妙な話は、いかにもSF小説に出てきそうな設定です。
しかし実は、この「並行世界(パラレルワールド)」の概念は、量子力学という現代物理学の基礎理論の解釈として、真剣に議論されてきた歴史があります。
これがいわゆる「多世界解釈(MWI)」です。
多世界解釈の根本的なアイデアは、「量子力学において生じる“重ね合わせ”のすべての可能性が、実際に現実として同時に存在する」というものです。
たとえば有名なシュレディンガーの猫の思考実験では「生きている猫」と「死んでいる猫」が同時に存在するという奇妙な状態が出現します。
しかし多世界解釈の立場では、「猫が生きている世界」と「猫が死んでいる世界」の両方が矛盾なく並行して実在することになります。
私たちの意識はそのうち片方しか認識できませんが、他方の世界は別の“あなた”がしっかり体験している──というわけです。
このように書くと「それはほとんどSFの話では?」と思われるかもしれません。
ですが、量子力学が抱える測定問題や、いわゆる「波動関数の収縮」をめぐる長年の謎をうまく回避できるということで、多世界解釈は科学者の間でも長らく魅力的な理論として支持されてきました。
とくに、全宇宙を量子系として扱う宇宙論的視点では「世界がどこかで“ひとつに定まる”ということのほうが不自然だ」と考える研究者も少なくありません。
多世界を想定したほうが量子力学が抱える「測定問題」をシンプルに解決できるからとも言えます。
私たちが観測する前までは“不確定”だった状態が、なぜ観測した瞬間に特定の結果に収束するのか──この不思議を「実は結果がすべて同時に現実となり、私たちの意識はそのうち一つを体験しているだけ」と説明できるのが、多世界解釈の強みなのです。
デイヴィッド・ドイッチュ(David Deutsch)の著書『The Fabric of Reality(知の織物)』や、マックス・テグマーク(Max Tegmark)の『Our Mathematical Universe(数学的宇宙へのいざない)』など量子力学の第一線で活躍する研究者によって執筆された名著でも、多世界解釈が登場し、量子コンピュータの背後に潜む並行世界の可能性や、宇宙論的視点からみた多世界像が語られています。
しかし──そんな「みんな大好き」な多世界解釈が、今、思わぬ方向から“危機”にさらされています。
英ブリストル大学のサンディ・ポペスク教授とダニエル・コリンズ博士による新たな研究によって、量子力学における最重要な原理のひとつとされる「保存則」に関する新しい研究が、「多世界を仮定しなくても、あるパラドックスが解消できるかもしれない」と主張し始めたのです。
多世界解釈は物理学の根幹となる「保存則」において、他の説より有利な位置にいることが拠り所となっていました。
なのに「一つの世界だけで保存則が守られる」ことが論理的に示せるなら、「分岐」や「並行世界」といったロマンあふれる話を支える柱が消えてしまうことになります。
今回は、こうした多世界解釈をめぐる新局面を「危機」としてとらえ、まずは量子力学の基礎をかみ砕きながら、なぜ多世界解釈という考え方がそもそも魅力的なのかを紹介します。
そのうえで、多世界解釈が登場した歴史的背景や、近年の理論的展開を概観し、Collins & Popescu の研究が提起した保存則について詳しく取り上げ量子力学の解釈問題がどこまで進んでいるのか、その最前線に迫ってみたいと思います。
「世界はひとつなのか、無数なのか?」という問いかけは、単なる空想の話ではなく、量子力学という理論が突きつける根源的なテーマのひとつです。
量子コンピュータや量子通信などの実用面だけでなく、現実とは何か、私たちの存在とは何かという哲学的・宇宙論的な視点にも関わってきます。
パラレルワールドへの扉を開き「みんな大好きな多世界解釈はいま本当に危機にあるのか?」を徹底解説します。
元論文
Conservation laws and the foundations of quantum mechanics
https://doi.org/10.1073/pnas.2220810120
ライター 川勝康弘(Yasuhiro Kawakatsu)
ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者 ナゾロジー 編集部
量子力学の基礎をざっくり理解する
古典物理学(主に中学や高校で習う古い物理学)では、リンゴが木から落ちる理由(重力)や、台車にかかる力と加速の関係(運動方程式)など、直感的に理解しやすい法則が多く見られます。
ところが、量子世界では測定や観測こそが系の状態を大きく左右する――むしろ、測定を行うことで「初めて」粒子の性質が定まる、という奇妙な性質が見られます。
古典物理学では「人間が観測をしようがしまいが、結果は変らない」とされていますが、量子力学の世界では人間が行う観測そのものが物理現象の中に組み込まれ、現象そのものを変質させてしまうのです。
そのため観測によって起こる問題は「観測問題」と呼ばれており、多世界解釈というアイディアを知るための第一歩となります。
ここでは、量子力学の基本原理と、そこから生まれた観測問題の概要を紹介します。
量子力学とは何か
量子力学では、電子や光子(光の粒子)などの極めて小さな存在を扱います。
古典物理学の視点に立てば、「電子はボールのような粒子で、光は波だ」という単純なイメージを抱きがちです。
しかし、実際には電子は波の性質を示し、光は粒子の性質を示すことがある、という驚くべき事実が明らかになりました。
たとえば有名な「二重スリット実験」では、1個ずつの電子を2つのスリットに射出すると、1個の電子が同時に2つのスリットを通過し、干渉パターン(しま模様)を形成するという不思議な実験結果が得られます。
つまり、発射するときには1個、観測されたときも1個なのに、その1個の電子が2つの穴(スリット)を同時に通過するのです。
この現象は、電子が「粒子」でありながら「波」の性質も持っていることを示しており、一つの電子が複数の経路を同時に通るという直観に反する挙動をとることを示しています。
(※この実験セットに限定すると、干渉パターンは量子的現象が起きたことを示す証拠にとして機能します)
さらに量子力学では、「ある状態」と「別の状態」が同時に存在する重ね合わせ(superposition)と呼ばれる概念が登場します。
たとえば電子のスピン(方向感覚のようなもの)が「上向き」と「下向き」の両方を同時にとり得る――それが重ね合わせです。
ただし、私たちが観測(測定)を行うと、結果は「上向きか下向きのどちらか一方」に定まる、というのが量子力学の実験的事実です。観測前は「複数の可能性を同時に抱えている」状態で、観測後はどこか一つに落ち着いてしまう。このプロセスが量子力学独特の世界観を生み出します。
シュレーディンガーの猫のパラドックスはこの重ね合わせの不思議を象徴する思考実験としてしばしば取り上げられています。
物理学者エルヴィン・シュレディンガーは、次のような装置を考えました。
『放射性物質があり、それが崩壊するかどうかは量子的な確率で決まるとし、もし崩壊が起こると、それを検知する機構が作動して毒ガスを放出し、箱の中の猫は死んでしまう。崩壊が起こらなければ毒ガスは出ず、猫は生存したまま』
量子力学の立場に立つと、放射性物質は「崩壊した状態」と「崩壊していない状態」の重ね合わせになり得ます。となれば、その結果に連動している猫も「生きている」と「死んでいる」の重ね合わせで存在しているはずです。
ところが、箱を開けて観測(測定)した瞬間には、猫は生きているか死んでいるかのどちらかに定まる。いったい、この“定まる”というプロセスはどう理解したらよいのでしょうか?
これこそが量子力学の「測定問題」であり、のちに多世界解釈が登場する大きなキッカケの一つとなります。
測定問題の核心
量子力学は、電子などの状態を「波動関数」という数学的な式で記述します。
波動関数は「その物体(や粒子)が、空間のどこに、どんな状態で存在するかを表す“可能性の分布を示す地図”のようなものです。
この可能性の地図を使うことで小さな電子、巨大分子フラーレン、そして人間すらも波動関数として描くことができます。
「人間なんて大きくて重いし、原子の集合体だから、波動関数なんてあるの?」と思うかもしれません。
しかし理論上は「人間にも波動関数は存在する」と言えます。
そのため1個人であっても、2つのスリットを同時に通過することも「理論上は」可能となっています。
(※ただしその波動関数はものすごく大きくて複雑ものになり、実際に人間の波動関数を書き出すことは極めて困難となります。また人間のように巨大な物体は内部の原子同士が相互作用して容易に「観測」と同じ状況が起きてしまうため、人間を波にするのも極めて困難となっています)
重ね合わせの状態にあるとき、この波動関数は収縮しておらず、空間のさまざまな場所に存在確率が分布している状態にあります。
電子がいくつもの場所に“ぼんやり”と存在しているイメージとも言えるでしょう。
しかしいざ観測を行うと、「その電子がここにいた!」と、突然、はっきり定まってしまいます。
これを「波動関数が収縮した」といいます。
また別の言葉では、量子的状態が崩壊したとも表現されます。
どちらにしても、重ね合わせ状態が、一瞬にして“ひとつの場所”や“ひとつの状態”へと絞り込まれるのです。
つまり波動関数の収縮とは、本来ならいろいろな可能性が同時に存在するはずの状態が、観測した途端に、ひとつの“実際の結果”へと確定してしまうように見える現象とも言えるでしょう。
この「収縮」は物理学者の立場でも議論が絶えず、根本的な疑問を生み出してきました。「測定装置が量子系に触れると何が起きるのか?」「観測とは何が決め手なのか?」など、数多くの解釈や理論的議論が展開されてきたのです。
そしてこの問題は科学哲学にも普及していきます。
猫の話に戻れば、「観測」が行われるまで猫は生と死を重ね合わせているのかもしれません。
しかし、もし箱の中の猫自身が「観測者」だとしたら?
あるいは「見ている人」以外にも観測者は成り立つのでは?
こうした突き詰めた問いが、「意識」と量子力学の結びつきまで論じる議論や、「観測者」と「被観測系」を同等に扱おうとするアプローチを生み出しました。
そこで登場したのが多世界解釈です。
多世界解釈(MWI)とは何か
前章で触れたように、一般的な量子力学の説明では「観測の瞬間に波動関数が収縮する」という不思議なプロセスが登場します。
しかし多世界解釈では「そもそも不思議な収縮など起こらない」とする主張が根底にあります。
多世界解釈の源流となったのは、アメリカの物理学者ヒュー・エヴェレット3世(Hugh Everett III)が1957年に発表した論文「“Relative State” Formulation of Quantum Mechanics」です。
彼は量子力学が従うシュレディンガー方程式が「常に成り立つ」ことに注目します。
通常の解釈では、「観測」という過程だけはなぜか特別扱いされ、そこだけ波動関数が収縮すると考えられていました。
エヴェレットは、なぜ観測だけが特別なのか、どうして自然界にそんな“二重基準”が必要なのか、と疑問を抱いたのです。
またエヴェレットはこの中で「波動関数の収縮」をあえて認めず、観測者を含む宇宙全体が常にシュレディンガー方程式による進化(ユニタリー進化)だけで記述されると提案しました。
ある意味で「シュレーディンガー方程式の普遍性と物理学にダブルスタンダードを許さない純粋さ」が多世界解釈誕生の原動力となったと言えるでしょう。
そして観測による波動関数の収縮を認めない代わりに、エヴェレットはあらゆる可能性が実現する「並行する世界」が次々に生まれると考えるとする多世界解釈に辿り着きます。
たとえば、シュレディンガーの猫に再び登場してもらいましょう。箱の中の猫が“生存する”可能性と“死ぬ”可能性がともにある状態では、観測(箱を開ける行為)が起こる前から世界はそれらを含んだ総合的な量子状態にあります。
そして観測が行われた瞬間に「猫が生きている」状態を観測する世界と、「猫が死んでいる」状態を観測する世界の両方が、ひとつの大きな量子状態の中で分岐する──つまり、「どちらの可能性も本当に起こっている」のです。
イメージとしては
分岐前:「生きている猫」+「死んでいる猫が」が重ね合わせとして共存している
分岐後:「猫が生きている世界線」と「猫が死んでいる世界線」が独立して存在する
となります。
多世界解釈は重ね合わせは否定しないものの、波動関数の収縮という(エヴェレットからみれば意味不明な)状況を認めないことを代償に、分岐する世界を創造したのです。
そしてその後は「猫が生きている世界線」と「猫が死んでいる世界線」が互いに触れ合うことなく、独自の歴史を辿ることになります。
この「収縮を認めない」アプローチは当初、物理学界からはあまり注目されませんでした。エヴェレット自身も若くして研究を離れ、表舞台にはほとんど出なくなってしまいます。
この時点で多世界解釈は有力な仮説としては死んだと言えるでしょう。
しかし後年、ブライス・デウィット(Bryce DeWitt)らの研究によって再評価され、いまや多世界解釈は量子力学の有力な解釈の一つとして広く知られるに至りました。
デウィットは、量子宇宙論や場の量子論の観点からも 多世界解釈が矛盾しないことを示そうとします。
特に重力を含む量子理論(量子重力)を考えた際に、観測者や外界との境界を曖昧にする必要があるとされ、コペンハーゲン解釈よりむしろ MWI の方が自然なのではないか、という議論が生まれました。
こうした流れは後にスティーヴン・ホーキング(Stephen Hawking)やマーティン・リース(Martin Rees)といった宇宙物理学者の議論にも影響を与え、宇宙論と量子基礎の接点で多世界論が取り上げられる下地となっていきます。
実際、ホーキングは、宇宙全体を量子力学的に扱い「宇宙の波動関数」を考えるアプローチを推進しました。これは、観測者を含むすべてを量子論で記述する多世界解釈的な発想に近い部分があります。
(※ホーキング自身が多世界解釈の信奉者という意味ではなく、彼の理論における波動関数の扱い方が多世界解釈に近いものがあるという意味です)
このように、多世界解釈は観測問題の説明として非常にシンプルかつ大胆です。
何しろ「収縮」という特殊な物理過程を廃して、波動関数の普遍的進化だけを認めればよいわけです。
しかし同時に、「世界が分岐して膨大な並行宇宙が存在する」という図式は、にわかには受け入れがたい壮大かつ哲学的なものとなりました。
にもかかわらず多世界解釈が、多くの物理学者や量子情報科学者から支持を集めているのは、後述するように測定問題や保存則といった量子力学の根本的な謎を“きれいに”統合できるためです。
次章では、なぜこのような魅力的な解釈がこれほど支持されているのか、その背景と理由をさらに掘り下げてみましょう。
なぜ多世界解釈は研究者にも「人気」なのか
なぜ多世界解釈が人気なのか?
SFファンの目線からみれば、基底世界を出発点にして分岐した世界線を旅する物語が魅力的に思えるからでしょう。
5秒前に分岐した世界、5年前に分岐した世界、50年前に分岐した世界……それぞれの世界を描くことそのものが、読者を惹きつけるからです。
さらにそこに主人公による「介入」ができたならば……それだけで妄想がいろいろ広がります。
しかし多世界解釈が量子力学の真面目な研究者からも支持を集めているのは、(当然のことですが)彼らが単にSFファンだからという理由ではありません。
研究者からも多世界世界が人気なのは、量子力学の測定問題をはじめ、理論全体のシンプルさや宇宙論との親和性など、いくつかの重要な要素があります。
まず先に述べた量子力学が抱える最大の難問となる「測定問題」です。
通常の解釈では、測定によって波動関数が“収縮”し、重ね合わせ状態が一つの実測値に確定すると考えます。
しかし「なぜ観測の瞬間だけ特別なのか?」「その“収縮”とは具体的にどんな物理過程なのか?」と問われると、納得のいく説明は難しく、物理学者たちは長年、頭を抱えてきました。
多世界解釈は、この収縮という不可解なプロセスをそもそも導入しないことで問題を回避します。
観測者と被観測系の間で起きるのはあくまで通常の量子相互作用であり、そこから生じる重ね合わせの拡大が「世界の分岐」として解釈されるのです。
極論すれば「どんな状況でもどんな場合でもシュレディンガー方程式は破れない(収縮しない)ため、常にシュレディンガー方程式に従うだけでよい、というシンプルさ」があるわけです。
また古典物理学との相性の良さも人気の理由となっています。
古典物理の世界では、観測しようがしまいが結果は同じというスタンスをとります。
多世界解釈は重ね合わせは否定しませんが、重ね合わせ状態に対する干渉項目が事実上ゼロになる、つまり分岐した世界線同士が互いに干渉しなくなるため、観測者からは他の分岐が見えなくなり、自分のいる世界では結果として古典物理に従っているようにみえるのです。
さらに多世界解釈は小さな量子の世界と日常の大きな世界を連続的に考えることを可能にします。
「測定時の収縮」を省くことで、「どこからが量子でどこからが古典か?」という問題を回避できるのは大きな魅力と言えるでしょう。
そして先に述べたように、多世界解釈は最先端の宇宙論とも親和性が高いことも特徴となっています。
たとえば宇宙全体を一つの巨大な量子系としてみなしたとき、「ビッグバンの時点からすべての可能性が重ね合わさり、そのまま現在まで分岐し続けている」という壮大な絵が描けるのです。
この場合、宇宙のどこにも観測者や測定の特別な境界を設けることなく、さまざまな現象に対して純粋に量子力学を適用することが可能になります。
またもし波動関数が宇宙全体を記述するなら、複数の歴史や未来が同時に展開されることも不思議ではないことになります。
こうした視点は、現代の物理学者にとって新たな理論構築の可能性を示唆します。
たとえば、マルチバース理論(多宇宙論:注意・多世界解釈とは別理論)やインフレーション理論などとの組み合わせで、宇宙の始まりや構造を考察する際に、多世界解釈を意義深いツールとみなす研究者もいます。
これらの理由から、多世界解釈は「奇抜だけれども深い理論的整合性を持った解釈」として多くの人を魅了してきました。
観測時の不思議な収縮を排除できるシンプルさ、そして古典物理学や宇宙論との連続性を強調できる点が、高く評価されているのです。
人間で例えるならば「変わり者だけど変わり者なりに筋が通っている人」のようなものです。
そのような人は、使い方次第では社会に有益なように、物理学の世界でも多世界解釈の視点を道具として使うことで、理論的発展に有益となるのです。
理論としてもロマンがあり、理論ツールとしても強力であるとなれば、研究者目線でも人気が出て当然でしょう。
多世界解釈と保存則
これまで見てきたように多世界解釈は「量子力学における観測問題」を世界線の分岐という力技でスッキリと解決する大胆な理論です。
しかし、量子力学の問題は観測だけではありません。
観測問題ほど有名ではありませんが、実は量子力学には「エネルギーや運動量に対する保存則」にも問題を抱えていました。
古典力学や電磁気学、相対性理論など、近代物理の根幹を成す方程式群は、エネルギー保存や運動量保存を大前提としています。
たとえばある野球選手が野球場でボールを投げた場合、野球選手からはボールを投げるのに使ったエネルギーが失われます。
ボールを際限なく投げ続ければ、選手からエネルギーが失われ続け、やがて疲れて倒れてしまうでしょう。
しかし野球場を含む空間全体から見た場合、野球選手が失ったエネルギーは飛んでいくボールや、そのボールが命中した壁に移っただけであり、空間全体の持つエネルギーの総和は保たれたままとなります。
あるいは走っている車がブレーキをかけると、車の速度は減少して運動量がなくなります。
この場合、車は野球選手の例ように外部の何かにエネルギーを出力しているわけではないので、車の失った運動量がどうなったかは視覚的にはよくわかりません。
しかし減速していく過程で、車の運動エネルギーは完全に消えるわけではなく、ブレーキパッドやディスク、タイヤなどの摩擦によって熱エネルギー(さらに音や摩耗の形で微小なエネルギー)に変換されているのです。
急ブレーキを踏んだ車が甲高い音を立てるのも、運動エネルギーが音エネルギーに変換されている証拠と言えるでしょう。
このようにエネルギーや運動量は形を変えて移り変わっても、その総和は変らないというのが保存則になります。
保存則は物理学の最重要の柱とも言われ、実験的にも無数の検証が積み重ねられてきました。
量子力学でも、シュレディンガー方程式にハミルトニアン(エネルギー演算子)を定義すれば、閉じた系ではエネルギーが保存されることが示されます。
しかし、実際には“測定”という操作が、演算子の固有状態へと波動関数を“突然”写し替えてしまう(射影測定)というコペンハーゲン的解釈のステップがあるため、「あれ、保存則が破れているのでは?」と思える場面が出てきます。
たとえば、ある粒子の運動量を測定するとき、測定の前は「運動量がいろいろな値の重ね合わせ」だったかもしれません。
ですが測定によって「1つの値」に定まるなら、その前後で“見かけ上”運動量が変化したように見えます。
もちろん、装置が粒子と相互作用することで運動量がやり取りされる、と考えれば説明は可能です。
問題は、その「やり取り」のメカニズムを量子力学的に厳密に追求したときに、通常の解釈では「観測に伴う波動関数の収縮」が追加で必要となる点です。
先に触れたシュレディンガーの猫でも、放射性崩壊が起きるか否かというプロセスが重ね合わせになるとき、系全体のエネルギーの扱いが微妙になります。
測定をして「猫が死んでいる」とわかった瞬間、その間にどこかで崩壊エネルギーが放出されたはずですが、猫が死んでいない枝では崩壊エネルギーの放出そのものが起きていません。
もし重ね合わせ状態が“一つの結果”へと収縮するなら、もう一方で想定されていたエネルギーの行方はどうなるのでしょうか?
ジョン・フォン・ノイマンも論文にて、このように「測定によって保存則が一瞬破れるかのように見える現象」について指摘しており、観測問題と併せて保存則問題は研究者たちの頭を悩ませています。
というのも、量子力学の予測は本質的に確率的であり、多数回の実験を行ったときの「統計平均」では保存則が満たされると考えられています。たとえば100回、1000回と同じ測定を繰り返して得られる平均値は理論と合致するでしょう。
しかし「たった一度きりの測定」に着目したとき、果たして保存則をどう考えればいいのか?という疑問が浮かびます。
古典的な直感なら、「1回の測定においても保存則は破れないはずだ」と思いたいところですが、通常の量子論的には「重ね合わせ状態のどの要素が実現するかは確率的」という説明にとどまってしまうことも多いのです。
しかし多世界解釈はこの問題を鮮やかに解決しています。
多世界解釈では、観測の結果が複数あればそれぞれの可能性がすべて別の世界で実現すると考えます。
したがって、運動量が“突然増えた”ように見える結果が出ても、並行世界のどこかでは“減った”世界があるかもしれない。それらをすべて合わせて考えれば、トータルの保存則は破れていないと解釈できるわけです。
「たった一度きりの測定」で異常に高い運動量が観測されて保存則が破れているように見えても、その「たった一度きりの測定」は無数の世界線をうみだし、その中に異常に低い運動量が観測された世界線もあるため、最終的な保存則は守られるわけです。
あえておみくじで例えるならば、大凶を引き当ててしまった不運を帳消しにするため、別の世界線では大吉を引き当てている自分がいる状態とも言えます。
(※言うまでもなく「運」や「確率」はエネルギーや運動量と違いもともと保存則に当てはまりません。あくまで異常に高い結果は異常に低い結果で補われるという点を強調したたとえです)
多世界解釈を信じる研究者たちも、多世界解釈においては「いくつもの測定結果が生じる世界を合わせて考えれば、運動量などが保存される」と説明するのが典型的でした。
このような量子力学の保存則問題に対する筋が通った解釈は、ある意味で多世界解釈の優位性を示すだけでなく、多世界解釈を支える大黒柱として機能してきました。
しかし新たな研究により、この大黒柱が揺らぐことになり、多世界解釈は危機を迎えました。
多世界解釈の危機
これまで扱ってきたように、量子力学には「測定による波動関数の収縮」という不思議なプロセスがあり、これをどう解釈するかが大きな論点となってきました。
また、同時に「観測時に保存則が破れてしまうかもしれない」というパラドックスがあり、多世界解釈(MWI)は「宇宙が測定のたびに分岐しているから、全体としては保存則が保たれる」という視点でこの問題に答えようとしてきました。
ところが近年、イギリス・ブリストル大学のサンドゥ・ポペスク(Sandu Popescu)とダニエル・コリンズ(Daniel Collins)が主導する研究によって、「単一世界」であっても、保存則は破れていない可能性があると示唆されました。
重ね合わせを発生させる装置を考慮に入れる
Collins & Popescuは2020年代初頭ごろから続く一連の研究の中で、「測定による保存則の破れ」と見なされてきた現象を、より広い視点で捉えなおすという試みを続けていました。
通常、実験では電子や光子を特定の量子的状態に準備する段階が必要です。
たとえば特定のスピン状態や特定の運動量状態などを作り出すレーザーや電磁場があり、こうした重ね合わせを作る装置(状態準備装置)を「プリペアラー」と呼ぶことがあります。
(※プリペアラーには重ね合わせ以外にもさまざまな量子的状態を作るものが含まれます)
多くの人は、測定器(例:検出器)と被測定系(例:電子)の相互作用ばかりに注目しがちですが、実際にはプリペアラー(状態準備装置)もまた量子系であり、被測定系とエンタングルメント(量子もつれ)を形成している可能性があります。
Collins & Popescuは、このプリペアラーが見過ごされてきた点こそが、保存則の破れを招いているように見える根本原因ではないかと指摘しました。
たとえば「重ね合わせ状態を作り出す装置」は、その粒子と何らかの相互作用をしているため、量子力学的には“系+プリペアラー”の間でエンタングルメントが生じていると考えられます。
つまり、単純に「粒子だけが重ね合わせ状態になっている」のではなく、「粒子とプリペアラーが一体となって重ね合わせ状態を共有している」のです。
ここが重要なポイントです。
プリペアラーの側にも運動量や角運動量、あるいはエネルギーなどがやり取りされている可能性がある場合、測定によって粒子の運動量が特定の値になったとしても、その変化は「分岐した別の世界線ではなくプリペアラーが補償している」のではないか、というわけです。
この仮説を証明するためCollins & Popescuは理論モデルを組み立て、保存則を破っているように見える場合、それを補うのが別世界なのか、実験装置内の重ね合わせを作る装置なのかを調べました。
結果、破れたようにみえる保存則の埋め合わせが別世界ではなく、重ね合わせを作り出す装置によって行われていることが判明しました。
観測者や測定器が出番になるより先に「粒子を重ね合わせ状態にしておく装置(プリペアラー)」があって、そこからまだ少し残っているエンタングルメントが測定結果の“ズレ”を帳消しにしてしまうのです。
つまり「測定そのものより前の段階で粒子と装置が結びついているため、その結びつきが最終的な値を調整し、あたかも保存則が破れていないかのように埋め合わせさせるのだ」と彼らは主張しているわけです。
さらに衝撃的なのは、彼らが「これは単なる確率的なアベレージ(平均)として成り立つのではなく、“一回限りの測定イベント”においても成り立つ」と述べていることです。
従来、エネルギーや運動量の保存則は「多数回の測定を繰り返した統計的な結果として成立する」と考えるのが常識でしたが、Collins & Popescu は「各測定ごとに厳密に保存則が成立している可能性」を数理的に示しました。
この結果は、多世界解釈の整合性に大きな影響を与えます。
なぜなら、並行世界を仮定せずとも、単一の測定結果のなかで保存則を満たせる可能性が示唆されるからです。
もし本当に「単一の測定においてすら、保存則が破れていない」ならば、多世界解釈を支える大黒柱──「保存則を守るための枝分かれ仮説」──が崩壊することになります。
極論するならば「この世界だけで説明できるとすれば多世界解釈は必要ない」ということになります。
もちろん、これが即「多世界解釈を完全に否定する」という結論には直結しません。多世界解釈は「測定問題の収縮」全般を回避するための思想であり、保存則の問題だけがその存在意義ではないからです。
またCollins & Popescu は「多世界を否定」しているわけではなく、あくまで「単一の測定イベントでも保存則が守られる構造がある」と指摘しています。
しかし「多世界を導入しなくても保存則が成立する」のなら、「そもそも多世界を仮定する必要はあるの?」という問いが当然浮上してきてしまうでしょう。
まとめ「多世界解釈の危機は発展の痛み」
ここまでの章を通して、多世界解釈がなぜ“危機”にさらされているのか、そして量子力学の観測問題をめぐる新しい視点や研究の動向を見てきました。
古典的には「観測による波動関数の収縮」という不可解な要素を回避するため、多世界解釈がある種の“大胆な救済案”として注目を集めてきました。
しかしCollins & Popescu の新研究は、多世界解釈の中でも重要視されてきた「測定時における保存則の説明」を、単一世界のみで実現しうる道を切り開いた可能性があります。
これまで多世界解釈を支えてきた一つの柱──「測定で波動関数が収縮したように見える過程でも、宇宙全体が分岐することで保存則は破れない」という議論──が、もはや“MUST”ではなくなったとするならば、確かに「危機」と言えるでしょう。
ただし、冒頭にも述べたように、量子力学の解釈論争は非常に奥が深く、保存則のパラドックスが解消されてもなお「測定問題」「意識や観測者の役割」など、他にも難問が山積しています。
多世界解釈の将来がこれですべて否定されるわけではありません。
しかし、保存則の面から見た“独自の優位性”が薄れれば、多世界解釈を“どうしても選ばなければならない”という必然性が揺らぐのは確かです。
こうした状況変化は、量子力学のさらなる発展にとってむしろ健全なあるべき姿と言えるでしょう。
ある理論の優位性がいつまでも変わらなければ、それは信仰と同じであり、人類が理論的な発展をしていない証拠とも言えるからです。
むしろ多世界解釈をめぐる議論は、Collins & Popescu の成果が導火線となり、一部の研究者にとっては大きな転機をもたらすかもしれませんし、他の研究者にとっては単に別の視点を提供するだけで終わるのかもしれません。
重要なのは、こうした議論自体が量子力学の深淵をさらに掘り下げ、私たちの世界観を揺さぶり、思いもよらないアイデアや実験につながっていく可能性があるということです。
「みんな大好き」 といわれる多世界解釈は、確かに今、議論の矢面に立たされています。
しかし、それは量子力学の真理がさらに一歩先へ進むための健全な衝突でもあります。
未来の量子力学は、ひょっとしたら「もっと魅力的な多世界」かもしれないし、あるいは「ひとつしかない巨大な宇宙」の見方がいっそう明快になるのかもしれません。
どちらにせよ、量子論の旅はこれからも進んでいくでしょう。